「デジマ女子」サービス概要
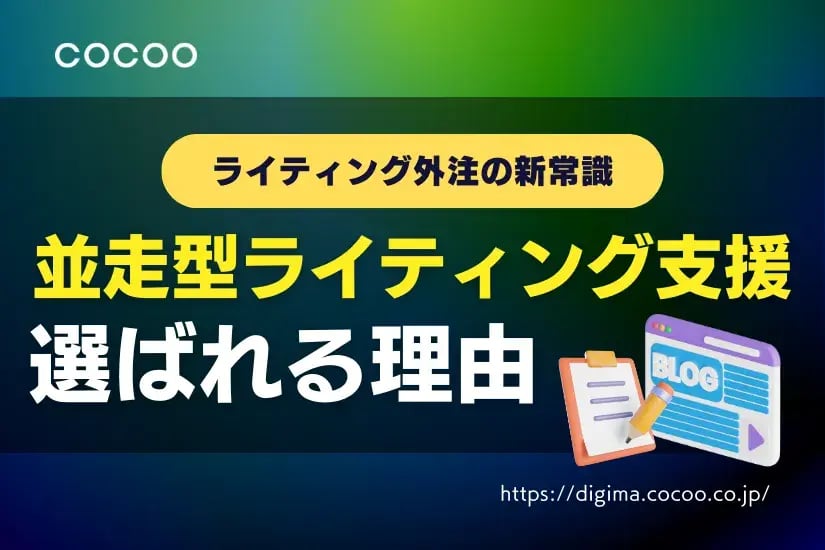
更新日:2025.10.02
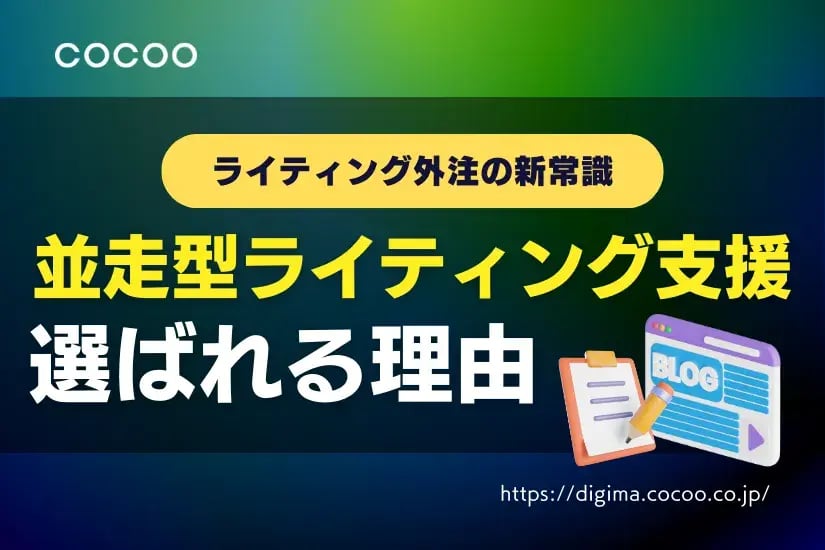
目次
こんにちは。今月のコラム担当、デジタルマーケティング事業部の草壁です。
今回のテーマは「ライティング外注の新常識」。
実は私たちのチームでも、過去に外部ライターへの依頼で思うような成果が出ず、何度も修正や社内調整を繰り返した経験がありました。
その中で感じたのが、“書いてもらう”ではなく、“一緒につくる”という考え方の必要性。
本記事では、私たちが実際に直面した課題と、それを乗り越えるきっかけとなった「並走型ライティング支援」について、リアルな視点からお話ししていきます。

ライティングを外注する企業の多くは、社内にSEOの専門チームを作るより、外部企業に任せたほうが質の高い記事が作れると考えています。
しかし実際には、思っていた内容と納品された記事がイメージと違ったり、修正や指示書の作成に手間を取られ、期待していた成果とギャップがあることは珍しくありません。
ここではまず、ライティング外注でよく見られる問題点やデメリットを整理します。
ライティング外注で特に多い課題のひとつが、自社ブランドに対する外部ライターの理解不足です。
単に指示書を渡すだけでは、社内では当たり前に伝わる顧客のニーズや表現トーン、専門用語の使い分けといった細かなニュアンスが共有しきれません。
そのため、思った以上にコミュニケーションに気を遣わないと、記事がただの一般論になってしまい、読者にまったく刺さらないで終わってしまいます。
多くの担当者は外注で記事作成の負担が減ると考えますが、実際は逆です。
実際は担当者が構成案や文体の調整といった外注先の対応に追われて、本来取り組むべき戦略立案や分析業務が後回しになるケースが多く見られます。
効率化のための外注だったはずが、かえって余計な手間を生む状況になってしまいかねません。
ライティング外注で見落とされがちなのが、記事を公開した後の振り返りや改善です。
SEO施策において記事は公開して終わりではなく、その後の継続したリライトや内部リンクの調整を行って初めて検索順位が上がるものです。
しかし、多くの外注では納品までがライターの業務範囲なので、いくら社内で改善案が出ても、社内だけでは修正につなげることができません。

ライティング外注は一見すると手軽で効率的な手段に思えます。しかし、記事の修正や継続的な運用といった点で限界を感じる担当者が増えていることは事実です。
事実、ライティング外注を活用することで、SEOノウハウが社内に蓄積されず外部依存が強まるようでは問題があります。
そうした中で注目されているのが、自社でコンテンツをつくり、自社ライターを育てていく「ライティング内製化」という考え方です。
ライティング内製化とは、記事の企画や構成、キーワードの選定といったライティング業務を社内で完結できるよう、体制を整えることです。
SEOに必要なスキルや考え方を習得し、外注に依存せずコンテンツ運用を継続できることを目指します。
SEOライティングを社内で完結させるには、単に文章を書ける人材がいるだけでは不十分です。
例えばSEOライティングには、ターゲットに合ったキーワード選定や見出し・構成の構築力、コンテンツの流入数や検索順位を可視化・分析する技術力が求められます。
また、Webサイトを管理するには、HTML/CSSやCMS運用、アイキャッチや図解を作成するデザイン技術、コンテンツの品質を一定に保つ編集力を育成しなければなりません。
実は、社内でここまでの要件を満たすのは、想像以上に難易度が高くなります。
多くの企業が社内でのSEOライティング体制構築に挑戦していますが、高いハードルに挫折するケースも珍しくありません。
まず、SEOは習得すべき専門知識が多岐にわたるため、短期間でチーム全体に浸透させるのは簡単ではありません。
さらに、メンバー間でスキルにばらつきがある、客観的なフィードバックが難しいといった課題も、社内だけで克服するのは困難です。

これまでのライティング外注やSEO支援サービスでは、記事の納品まで・SEOのアドバイスだけ、といった限られたサポートを受けることが一般的でした。
しかし、部分的に専門家を入れただけでは、ライティング内製化の支援としては不十分です。
そこで、基礎から社内ライターを育成から運用の自立までサポートしてくれる並走ライティング支援に注目が集まっています。
並走ライティング支援とは、記事の企画や構成、キーワード選定といったSEOライティングを社内で完結できるよう支援するサービスです。
自社ライティングなら記事づくりのノウハウや判断力が蓄積し、自社の方針に合ったコンテンツを自分たちの手で作れるようになります。
並走ライティング支援は、外注のように記事を納品して終わりではなく、成果が出るまで二人三脚で伴走するスタイルが特徴です。
対話型のヒアリングで方針を柔軟に整理できたり、記事の執筆中もフィードバックがあり完成度が高まりやすい、コンテンツ運用全体を視野に入れた提案が受けられるなどの点が、外注との大きな違いになります。

並走ライティング支援は単なる外注と異なり、伴走しながらSEO記事作成をサポートする内製化支援サービスです。
そのため、価格や知名度で判断せず、自社の目的や体制に合った支援スタイルかどうかを多角的に確認してから依頼するようにしましょう。
並走ライティング支援を導入する際は、支援可能な範囲を必ず確認しましょう。
記事の企画立案からキーワードの選定、構成づくり、執筆の壁打ち、そして公開後のリライトや分析まで、依頼する企業によって支援の範囲は大きく異なります。
業界理解が深く、ターゲットの購買行動に精通しているパートナーであれば、コンテンツの精度を高めやすくなります。
そのため、サービスを比較するうえで、導入事例や支援実績が公開されていれば必ず確認しましょう。
具体的には、似た業界や課題への対応経験がある企業を選ぶことが重要です。
並走ライティング支援では、自社のワークフローやスピード感と支援側のスタイルが合っているかどうかを見極めることが大切です。
ミーティングの頻度、チャットやメール対応の柔軟性、修正の回数など、サポーターとのやり取りのしやすさを事前に確認しておきましょう。

ライティングの外注は、記事の量産手段としては有効ですが、ブランド理解のズレや担当者の負担を考えると、成果につながるまで手間も時間もかかります。
そこで今求められているのが、戦略立案から執筆、公開後の改善までを一貫してサポートする並走ライティング支援です。
SEOに特化した並走ライティング支援を通じて、企画から改善までを共に考え、成果につながるコンテンツ運用をお手伝いします。