WEBコンテンツ制作代行サービス
リリース後は、
分析 → ターゲットやコンテンツの見直し → 改善
を繰り返し、最適化する必要があります。
更新日:2025.11.27
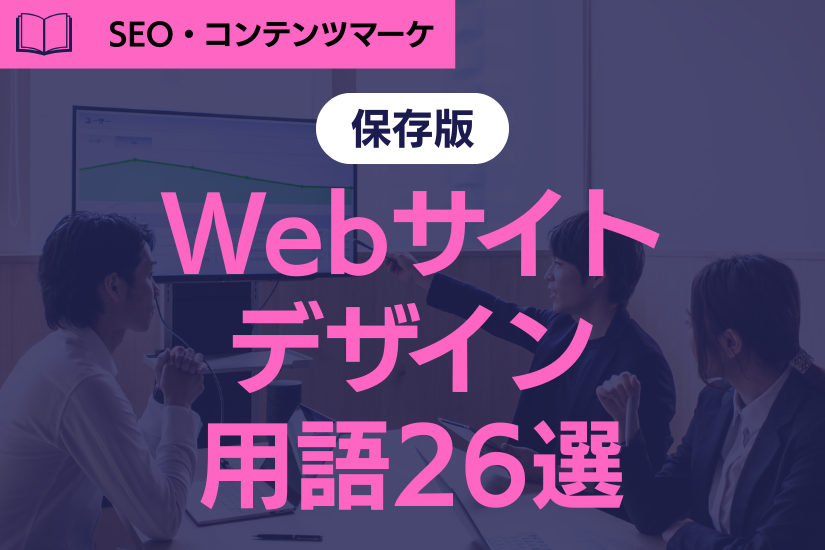
目次
Webサイトの役割は、単なる“会社案内”ではなく、集客・顧客体験・ブランド表現の中心へと進化しています。
そして、その変化を支えているのが Webデザイン です。
近年は、スマートフォン閲覧の比率上昇、アクセシビリティ(誰でも使える設計)、高速表示、ダークモード、AIを活用した自動レイアウト、ノーコードツールの普及など、制作環境が大きく変わりました。
その結果、Web制作に関わる人には “ただ見た目を作る” 以上の理解 が求められています。
それらを共有するための 共通言語 が、Webデザイン用語です。
この2026年版「Webデザイン用語集」は、
の3つの視点で、今押さえておくべきキーワードを整理しました。
制作を依頼する人も、提案する人も、この言葉が理解できれば “伝わるWebサイトづくり” が実現しやすくなります。ぜひ、日々の会話・要件定義・運用改善のヒントとして活用してください。

執筆:檜田詩菜(過去のインタビューはこちら)
コクーのマーケティング担当。鹿児島県出身。数年前まで美容コスメ・雑誌・不動産・IT業界の顧客マーケティングを担当。サスペンスLOVE。

まずは、Webサイト制作を依頼する前に準備しておきたいことを確認していきましょう。
制作依頼の段階で特に重要なことは、Webサイトを制作する目的です。
その根本となるきっかけを明らかにし、確認しておくことが大切です。
大前提として、Webサイトは商品のように「発注さえすればイメージどおりの完成品が届く」というわけではありません。Webサイトを構成する要素を決めるために、制作会社との情報共有が必要になります。
リリース後は、
分析 → ターゲットやコンテンツの見直し → 改善
を繰り返し、最適化する必要があります。
Webサイトは作ってリリースしたら終わり、というものではありません。
また、Webサイト内に情報や機能を詰め込みすぎると、のちの対応工数が増える原因にもなります。
Webサイト制作では、デザインの良し悪しだけでなく、構造・レイアウト・文字・色といった“見える要素の設計” を共通言語で理解する必要があります。
これらは、見た目を整えるためだけではなく、読みやすさ・理解しやすさ・企業らしさ をつくる土台です。
まずは、Webサイト制作者・依頼者の双方が押さえておくべき基礎用語から整理しましょう。
| 用語 | 簡易定義 |
|---|---|
| UI(ユーザーインターフェース) | 画面・ボタンなど、ユーザーが触れる部分の見た目と操作性。 |
| UX(ユーザー体験) | サイト利用時の使いやすさ・満足度・スムーズさなどの体験全体。 |
| レイアウト | 情報をどの位置に配置するか決める設計。視線誘導にも影響。 |
| ワイヤーフレーム | デザイン前の“設計図”。配置と構造を決める骨組み。 |
| ヒーローエリア | ページ最上部のメインビジュアル。第一印象と訴求を決める顔。 |
| ナビゲーション(メニュー) | ページ間を移動するための導線。迷わせない設計が基本。 |
| カラーパレット | ブランドや視認性を意識した色の組み合わせ。統一感を生む。 |
| フォント/タイポグラフィ | 文字の選び方・余白・サイズなど、読みやすさと印象を決める設計。 |
デザインは「美しい」だけでは成果につながりません。
問い合わせ・資料請求・購入などを増やすには、行動を後押しし、離脱を防ぎ、成果につながる仕組み が必要です。ここでは、ユーザー行動を想定した“実務で差が出る設計用語”を紹介します。
| 用語 | 簡易定義 |
|---|---|
| レスポンシブデザイン | デバイスに応じて表示が自動調整される設計。スマホ対応は必須。 |
| モバイルファースト | PCではなくスマホを基準にデザインする考え方。 |
| FID/CLS/LCP(コアウェブバイタル) | 表示速度・操作性などUXとSEOに影響する指標。 |
| CTA(Call to Action) | 行動を促すボタンや導線。文章・位置・色が成果を左右。 |
| コンバージョン導線 | CV(問い合わせ・購入)につながる動線設計。離脱防止が鍵。 |
| アクセシビリティ | 障害や環境に関わらず、誰でも使える設計思想。 |
| アルト属性(代替テキスト) | 画像説明文。SEOや音声読み上げに必要な要素。 |
| トーン&マナー | 表現の統一ルール。ブランドの“らしさ”を生む。 |
| マイクロコピー | ボタン補足やフォーム横の小さな言葉。行動率を変える要素。 |
| フォーム最適化 | 入力項目や段階設計によって離脱を減らす改善手法。 |
Webデザインは「流行を追う」だけではなく、技術の進化とユーザー行動の変化に合わせて進化する領域 へと変わっています。2026年は、アクセシビリティ基準・画像軽量化・ノーコード運用・AI支援など、使われ続けるサイト を前提にした設計が重要になります。
| 用語 | 簡易定義 |
|---|---|
| ダークモード対応 | 暗色表示に切替できる設計。スマホ利用でニーズ増。 |
| サステナブルWebデザイン | 過剰アニメや重い画像を避け、環境負荷と離脱を減らす設計。 |
| ノーコード/ヘッドレスCMS | コード不要で運用しやすい、高速表示CMSの仕組み。 |
| Webアクセシビリティ指標(WCAG) | 誰でも使えるWeb設計の国際基準。国内でも対応拡大。 |
| マイクロインタラクション | 小さな動きで操作をわかりやすくする演出。 |
| WebGL/3D表現 | 製品紹介などで没入感を生む表現技術。 |
| 画像最適化(WebP/AVIF) | 画像を軽量化し、表示速度とSEOを改善する手法。 |
| AIデザイン生成 | 配色やレイアウトをAIが提案・自動化する技術。 |

Webデザインは、見た目の美しさではなく 成果のための設計 へ。
2026年は、閲覧環境の多様化、AI活用、アクセシビリティ基準、運用の自走化など、企業が“育て続けるサイト”を前提に設計すること が求められます。
用語の理解は、制作側・依頼側が同じ方向を向くための“共通武器”です。