広告プランニング・運用代行サービス
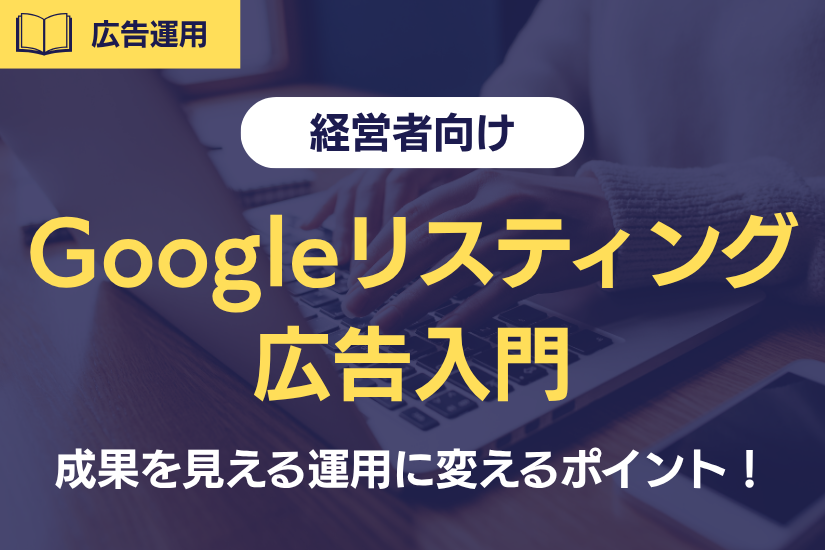
更新日:2025.10.16
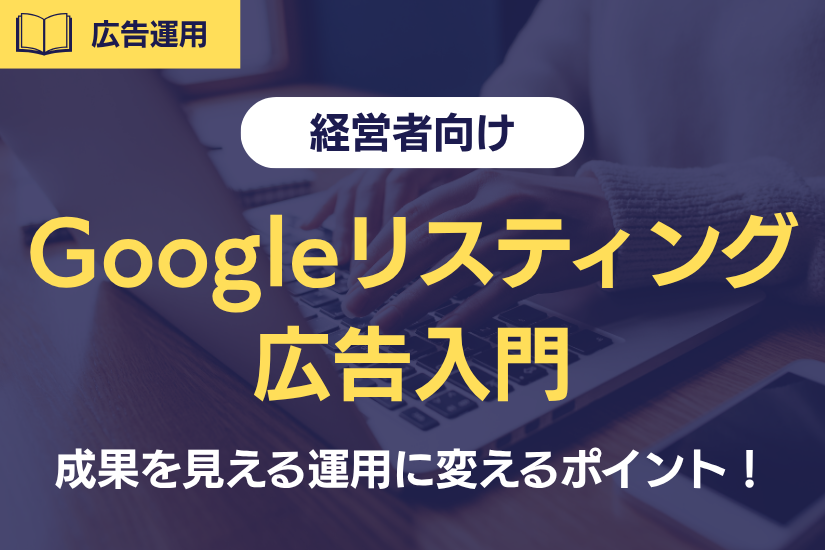
目次
広告費はかけているけれど、「何が成果で、どこを改善すればいいのか」がわかりづらい――そんなお悩みを耳にすることが増えました。
Googleリスティング広告は、設定や運用の仕方次第で成果が大きく変わる手法です。仕組みを理解しておくことで、外部パートナーに任せていても適切に判断・改善を促すことができます。
この記事では、経営層や責任者の方に向けて、2025年の最新動向とともに、リスティング広告の基礎と押さえておきたいポイントをやさしく解説します。

執筆:檜田詩菜(過去のインタビューはこちら)
コクーのマーケティング担当。鹿児島県出身。数年前まで美容コスメ・雑誌・不動産・IT業界の顧客マーケティングを担当。サスペンスLOVE。


リスティング広告とは、ユーザーがGoogleなどで検索したキーワードに連動して表示される広告のこと。
「知りたい」「買いたい」といった明確な意図を持つ人に向けて配信できるため、即効性が高く、成果が数字で見えやすいのが特徴です。
広告はオークション形式で配信され、キーワードの入札単価や広告文の品質などで順位が決まります。
つまり、単純な「金額勝負」ではなく、「設計力」と「改善力」で結果が変わる仕組みです。

リスティング広告は、単に「クリックを集めるための施策」ではありません。
経営の視点で見れば、投資対効果を明確にできる“デジタル営業”ともいえます。
ここでは、経営判断に関わる観点から、リスティング広告の主なメリットを整理します。
リスティング広告は、
をすべて数値で確認できます。
検索キーワードは、顧客が抱えている課題や興味そのものです。
どんな言葉で自社サービスを探しているかを分析することで、商品開発や営業戦略のヒントを得ることができます。リスティング広告は、マーケティングだけでなく、経営全体の意思決定に役立つ“市場データ”でもあります。
リスティング広告は、少額からでも配信可能です。
1日数千円単位でテスト運用を始められるため、リスクを抑えて検証→拡大のステップを踏めます。
新しいサービスの市場反応を探る「ミニマーケティング」としても有効です。
などを細かく設定できるため、限られた予算を“必要な層”に集中投下できます。
全国展開ではなく、地域特化型の企業でも十分な効果が期待できます。
リスティング広告は、SEOやSNS、LP(ランディングページ)施策とも親和性が高く、
「広告で集客 → LPで接客 → CRMでフォロー」という流れを構築しやすい手法です。
数値がすぐに可視化されるため、「投資→結果→改善」のサイクルを短期間で回せます。判断の速い企業ほどリスティング広告を武器にしており、データドリブンな経営に欠かせない仕組みとなっています。
.png?width=1920&height=600&name=%E5%BA%83%E5%91%8A%E3%83%90%E3%83%8A%E3%83%BC%20(7).png)
デジタル広告の世界は、ここ1〜2年で大きく変わりました。
特に2025年は、AIによる自動運用が急速に進んでいます。
経営層として押さえておきたいのは便利になった一方で可視化しづらくなった領域が増えているということです。
Google広告では、検索・ディスプレイ・YouTubeなどを横断的に配信する「P-MAX(パフォーマンス最大化)」が主流になりつつあります。
AIが自動で最適化を行うため、運用担当者の手間は減りますが、
が見えづらくなるという課題も。
つまり、数字は動いてもその理由が説明できない状態が起こりやすくなっています。
経営としては「自動化に任せる領域」と「人が分析・判断する領域」をきちんと分けることが重要です。
2025年春、Googleの検索結果ページのデザイン変更により、広告の表示位置が流動化し、CTR(クリック率)が全体的に下がる傾向が見られました。
一見すると成果が落ちたように見えますが、実際には「表示回数が増え、認知効果が上がっているケース」もあります。
大切なのは、CTRだけでなく
まで見たうえで、成果を多面的に判断すること。
2025年中盤のアップデートでは、ショッピング広告で「ブランド指定」が制限され、AIが自動的に商品を最適化する仕様に変わりました。
また、Google検索パートナー(提携サイト)への配信結果も以前より見えにくくなっています。
こうした状況では、代理店任せにせず、配信レポートでどこに出ているかを定期的に確認する仕組みが必要です。
見えない配信面に無駄な費用が流れていないか、「確認できる運用設計」そのものを整えることが、経営上のリスク管理につながります。
自動入札(目標CPA・目標ROASなど)は、十分なデータが蓄積されると高い効果を発揮します。
一方で、データ量が少ない初期段階ではAIの学習が不安定になりやすい点に注意が必要です。
経営としては、「データがたまるまでは手動で調整し、安定してから自動化に切り替える」
という運用ポリシーを明確にしておくと、成果の波を小さく抑えられます。
AI時代の広告運用では、「人が見るべきレポート」と「AIが自動調整する部分」を分けて管理することがカギになります。Power BIやLooker Studio(旧:データポータル)を使って、経営層でも一目で判断できるダッシュボードを整える企業も増えています。
可視化によって、「広告費=投資」としての意思決定がスムーズになり、代理店や社内チームとの認識のズレを減らせます。
2025年現在、Cookieレス時代に向けた計測方式(コンバージョンAPI・Consent Mode v2など)が本格化しています。これにより、従来のCV(コンバージョン)データが正確に取れないケースも発生。
経営としては、「計測方法が変われば数値も変わる」という前提を理解し、短期的な数値の上下で焦らない姿勢が求められます。
💡POINT
AIの進化によって“運用の手間”は減りましたが、同時に“判断に必要な情報”は見えにくくなっています。
経営層に求められるのは、「広告の仕組みを理解し、どの数字を見るべきかを見極める力」です。
広告代理店や社内の担当者に任せきりにせず、「何を目的に」「どんな指標で」成果を評価するのかを、経営として定義しておきましょう。

Googleリスティング広告は、今や「AIが最適化してくれる便利な仕組み」ではなく、経営の意思決定に直結する投資データとして活用できる領域になっています。
AI運用が進むほど、表面的な数値だけを追っていると「なぜ成果が出たのか」が見えにくくなります。
一方で、広告の仕組みを理解し、目的と指標を自社で定義できる企業は、代理店任せでもブレずに成果を積み上げています。
重要なのは、“運用をすること”ではなく、“成果を見極められる体制をつくること”。
経営層が広告を正しく理解することが、最終的には社内のマーケティング力を高め、事業の意思決定スピードを上げることにつながります。
当社では、今抱えていらっしゃる課題をしっかりと把握し、解決のご提案・対応させていただくデジマ女子というサービスがございます。
広告代理店とのコミュニケーション整理から、数値レポートの見える化、改善施策の企画までを企業の一員として伴走します。
広告成果を社内で“見える化”したい
代理店とのレポートが難しくて判断できない
自社でも広告を少しずつ理解・内製化していきたい
そんな課題を感じている経営層・責任者の方は、ぜひご相談ください。
“任せっぱなし”から“見える経営”へ──デジマ女子が伴走します。